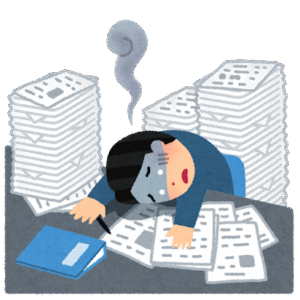2025年6月、熱中症対策が義務化!企業が準備すべき5つの対応とは?
2025年6月1日、労働安全衛生規則の改正により、職場における熱中症対策が“努力義務”から“法的義務”へと格上げされます。
これまで「安全配慮の一環」で行っていた熱中症対策が、今後は明確に企業の責任として規定され、未対応の企業には労働基準監督署からの是正勧告や労災責任が問われる可能性も出てきます。
本コラムでは、法改正のポイントと、企業の人事担当者が今から準備しておくべき実務対応を「5つのステップ」に整理してご紹介します。
🔶改正の背景:なぜ今、義務化なのか?
近年の気候変動により、夏の高温多湿状態が深刻化しています。2023年には、熱中症による労災の死傷者が1,195人にのぼり、過去最多を記録。死亡災害も3年連続で30人を超えています。多くは初期症状の見逃しや対応の遅れが原因です。
こうした状況を受けて、厚生労働省は2025年6月より**「熱中症が起きるおそれのある作業」に対し、事業者に明確な対応義務を課す改正**を行いました。
✅義務の対象となる職場とは?
まず重要なのは、「すべての職場が対象ではない」という点です。以下の2条件を同時に満たす作業が「義務対象」となります。
▶【1】環境条件:WBGTが28℃以上または気温31℃以上
- WBGT(暑さ指数)とは、気温・湿度・日射などを総合した暑熱リスクの指標
- WBGT28℃を超える場所は、屋外だけでなく、空調のない倉庫・工場・厨房など屋内作業場も含む
▶【2】作業条件:継続して1時間以上、または1日4時間以上の作業
- 不定期作業や短時間作業は原則除外
- ただし臨時作業でも該当条件を満たす場合は対象
⚠ オフィス内の座り作業や短時間の出張作業などは、これらの条件に該当しなければ義務の対象外です。
📝企業が準備すべき「5つの対応」
① 報告体制の整備(新設:安衛則612条の2第1項)
- 熱中症の自覚症状や周囲の異変に気づいた場合、即時に報告できる体制を整備
- 報告先(責任者名・連絡手段)を、掲示・朝礼・文書配布などで周知
- バディ制(ペア作業)や巡視の強化、ウェアラブル端末の活用も推奨
🔍ポイント:「誰に」「どのように」「いつ」報告するかを明文化
② 対応手順の策定と周知(新設:安衛則612条の2第2項)
- 熱中症が疑われた際の作業離脱・身体冷却・医療搬送などの流れをマニュアル化
- 回復後の体調急変にも備え、フォロー連絡の体制を記載
- 作業者への教育・研修を通じて、実効的な周知を徹底
🧊例:「水をかけて送風する」「冷房休憩所へ」「意識変化あり→即救急」
③ WBGT(暑さ指数)の把握【義務ではないが実質的に必須】
- 原則、作業場所でJIS規格のWBGT指数計による測定が望ましい
- 測定が困難な場合は、環境省の「熱中症予防情報サイト」や天気アプリでも代替可
- 作業着・保護具により「着衣補正値」を加えて判断
⚠測定が「義務」ではなくても、28℃を超えるかどうかの判断材料として事実上必要
④ 健康診断・個人リスクへの配慮
- 健康診断で異常があった場合(糖尿病・高血圧・心疾患など)、産業医の意見をもとに就業制限や業務配慮を検討
- 皮膚疾患や精神疾患もリスク要因
- 朝食抜き・睡眠不足・前夜の飲酒なども体調チェックの対象に
👩⚕️産業医の定期面談・衛生委員会での情報共有がカギ
⑤ 教育と訓練の実施(雇入時・職長教育にも組み込み)
- 作業者・管理者を対象に、以下の内容を含めた教育を義務化
- 熱中症の症状と初期対応
- 報告・救急体制の流れ
- WBGTや気温情報の活用方法
- 発症事例と反省点の共有
📄教育記録の保管までは義務ではないが、指導履歴の確認が求められる可能性あり
❓よくある誤解と実務上の注意点
| 誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 「WBGT測定はすべての会社で義務化された」 | ✕ 測定義務は対象作業に限られる。ただし、判断根拠として測定が実質必須に。 |
| 「冷房があるから大丈夫」 | ✕ 局所的な高温環境、服装、作業強度も加味すべき。 |
| 「短時間作業なら関係ない」 | ✕ 1時間以上または1日4時間超が目安。臨時でも条件を満たせば対象。 |
✅まとめ:熱中症対策は「命を守る労務管理」
今回の法改正は、罰則のためではなく、現場の命と健康を守ることを目的とした制度設計です。
人事部門としては、以下の3つを軸に準備を進めてください。
- 「熱中症の恐れがある作業」があるか把握
- 報告体制と対応マニュアルを整備・周知
- 産業医・衛生委員会と連携して継続的に改善
熱中症は「予測できるリスク」です。組織的な備えが、従業員の安心と企業の信頼を守る第一歩になります。
投稿者プロフィール

-
しながわ産業医オフィス 代表産業医
産業医としてこれまでに延べ3,000名以上の従業員の健康管理に携わる。
<保有資格>
泌尿器科学会認定専門医・指導医
テストステロン治療認定医
最新の投稿
 産業医コラム2026年1月31日職場における花粉症対策 ― 生産性低下を防ぐために ―
産業医コラム2026年1月31日職場における花粉症対策 ― 生産性低下を防ぐために ― お知らせ2025年12月27日年末のご挨拶
お知らせ2025年12月27日年末のご挨拶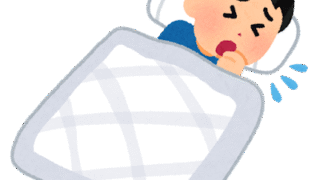 産業医コラム2025年11月30日冬の感染症対策2025:職場で防ぐインフル・ノロの集団感染
産業医コラム2025年11月30日冬の感染症対策2025:職場で防ぐインフル・ノロの集団感染 産業医コラム2025年10月23日ストレスチェック制度の運用ポイント――人事が押さえるべき視点を解説!
産業医コラム2025年10月23日ストレスチェック制度の運用ポイント――人事が押さえるべき視点を解説!