健康診断、受けっぱなしになっていませんか?――人事が押さえるべき健診事後措置の実務
年1回の定期健康診断(安衛法第66条)は、すべての企業に義務づけられた重要な制度です。
しかしながら、「とりあえず受診させればOK」という認識にとどまっていませんか?
企業には、健診の結果を適切に管理し、必要な事後措置を行う責任があります。
本コラムでは、健診結果の基本的な見方と、企業が行うべき事後措置の流れを解説します。
◆ 健康診断の基本構成と評価の見方
定期健康診断の主な項目には、以下のような検査があります。
- 身体計測(身長・体重・腹囲・BMI)
- 血圧
- 血液検査(血糖、脂質、肝機能、腎機能など)
- 尿検査
- 胸部X線
- 心電図 など
✅ 判定結果の読み方(例:A〜D判定)
| 判定 | 意味 | 企業の対応 |
|---|---|---|
| A | 異常なし | 対応不要 |
| B | 軽度異常 | 次回健診時に再確認 |
| C | 要再検査・生活改善 | 保健指導 |
| D | 要精密検査・治療 | 医療機関での再検査推奨(=受診勧奨)、産業医面談 |
※EやFといった判定が出る健診機関もあります。E判定やF判定は健診機関ごとに定義のばらつきがあるため今回は割愛します。
◆ 健康診断後に企業がすべき「事後措置」とは?
健康診断の実施後、企業は以下のような事後対応を取ることが法律で求められています。
✅ 1. 結果の通知(安衛法第66条の6)
すべての受診者に健診結果を通知する義務があります。
健康管理クラウドシステムの活用も有効です。
✅ 2. 所見ありの場合の医師意見聴取(安衛法第66条の4)
「要受診」や「要就業制限」と判定された場合、産業医による意見聴取(産業医面談)を行う必要があります。
✅ 3. 保健指導・受診勧奨(安衛法第66条の7)
産業医・保健師などによる生活習慣改善や再検査の案内を実施します。
✅ 4. 就業上の措置(安衛法第66条の5)
以下の3区分で判断し、必要に応じて対応します。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 通常勤務 | 通常通り勤務可 |
| 就業制限 | 作業軽減、深夜勤務回避、時短勤務などが必要 |
| 要休業 | 治療のため勤務継続不可 |
◆ 衛生委員会での報告もお忘れなく
事後措置を行った内容は、衛生委員会での報告と審議が推奨されます(個人情報保護の配慮を前提に)。
報告内容の例:
- 受診率
- 有所見率(C/D判定の割合)
- 所見の多い項目
- 就業制限者の発生有無
◆ 二次健診と特定保健指導の制度
特に、一次健診の結果で血圧・脂質・血糖・BMIに異常所見が重なった場合、労災保険の「二次健康診断等給付制度」の対象となり、追加の検査と特定保健指導を無料で受けられます。
✅ 特定保健指導の分類
| 支援レベル | 内容 |
|---|---|
| 情報提供 | 健康情報の配布のみ |
| 動機付け支援 | 面接+アドバイス(1回) |
| 積極的支援 | 継続的サポート(3〜6ヶ月の面談) |
このような二次検診や特定保健指導も活用しながら、従業員の健康管理体制を強化していくことがおすすめです。
◆ よくあるトラブルと防止策
| トラブル事例 | 予防策 |
|---|---|
| 健診結果の放置 | 結果通知後1ヶ月以内に産業医面談を促す |
| 就業制限対象者が通常業務を続けている | 就業区分のフローを整備・人事と共有 |
| 個人情報の漏洩 | データ管理ルールの明文化・周知徹底 |
◆ まとめ:健診後の対応こそが“健康経営”の実践
企業にとって、定期健康診断は単なる法定義務ではなく、職場の健康リスクを見える化し、早期対応につなげる大切なチャンスです。
人事担当者は、「受診させて終わり」ではなく、
- 健診結果の正しい理解
- 産業医との連携による事後措置
- 保健指導や受診フォロー
- 衛生委員会への報告
といった一連のプロセスを“抜け漏れなく”行うことで、従業員の健康保持と職場の安全衛生体制の強化に大きく貢献できます。
健康診断の事後措置対応に悩んでいる企業担当者様に少しでもお役に立てたら幸いです。
投稿者プロフィール

-
しながわ産業医オフィス 代表産業医
産業医としてこれまでに延べ3,000名以上の従業員の健康管理に携わる。
<保有資格>
泌尿器科学会認定専門医・指導医
テストステロン治療認定医
最新の投稿
 産業医コラム2026年1月31日職場における花粉症対策 ― 生産性低下を防ぐために ―
産業医コラム2026年1月31日職場における花粉症対策 ― 生産性低下を防ぐために ― お知らせ2025年12月27日年末のご挨拶
お知らせ2025年12月27日年末のご挨拶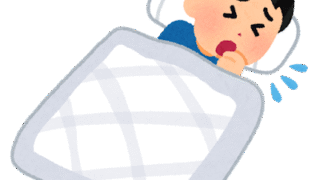 産業医コラム2025年11月30日冬の感染症対策2025:職場で防ぐインフル・ノロの集団感染
産業医コラム2025年11月30日冬の感染症対策2025:職場で防ぐインフル・ノロの集団感染 産業医コラム2025年10月23日ストレスチェック制度の運用ポイント――人事が押さえるべき視点を解説!
産業医コラム2025年10月23日ストレスチェック制度の運用ポイント――人事が押さえるべき視点を解説!


