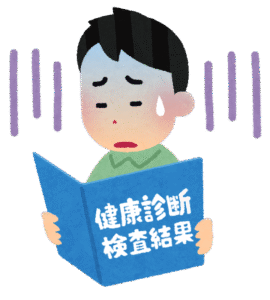日焼け止めだけじゃ不十分!?職場で取り組むべき紫外線対策
◆ はじめに:紫外線は労働衛生の課題
紫外線は「夏のレジャー時だけ注意すればよい」というイメージがありますが、実際には屋外作業はもちろん、屋内勤務でも窓際や外回り業務で日常的に曝露しています。
長期的には皮膚の光老化や皮膚がん、白内障のリスクを高め、短期的にも日焼けや炎症、免疫低下を引き起こします。
職場での紫外線対策は、従業員の健康保持だけでなく、労災予防や企業の安全配慮義務の観点からも重要です。
◆ 紫外線の基礎知識
太陽光に含まれる紫外線は波長によって3種類に分けられます。
| 種類 | 特徴 | 健康影響 |
|---|---|---|
| UVA | 波長320〜400nm。雲や窓ガラスを通過しやすく、真皮まで到達。 | シワ・たるみ(光老化)、皮膚がんリスク |
| UVB | 波長280〜320nm。表皮に強く作用。 | 日焼け(紅斑)、DNA損傷、皮膚がん |
| UVC | 波長100〜280nm。オゾン層で吸収され、地表には届かない。 | ― |
特にUVAは年間を通じて降り注ぎ、屋内でも曝露する点が見落とされがちです。
◆ 紫外線の曝露パターンとピーク時期
- 時間帯:午前10時〜午後2時で1日の約60%
- 季節:4月から増え、5月〜初夏にピーク
- 環境条件:
- 新雪:反射率80%
- 砂浜:10〜25%
- 水面:10〜20%
- コンクリート:10%
- 高度:1000m上昇ごとに紫外線量は約10%増加
つまり、真夏以外や曇天、屋内勤務でも一定量曝露していることになります。
◆ 紫外線の健康影響(エビデンスに基づく)
① 皮膚への影響
- 急性:日焼け(紅斑)、炎症、水ぶくれ
- 慢性:光老化(しみ・しわ)、皮膚がん(有棘細胞癌、基底細胞癌、悪性黒色腫)
② 眼への影響
- 白内障、翼状片、雪目(紫外線角膜炎)
③ 全身への影響
- 免疫抑制(感染症リスクを増加させる報告あり)
◆ 職場における紫外線対策の重要性
厚生労働省「紫外線環境保健マニュアル2020」によると、屋外作業従事者は一般人口より皮膚がんのリスクが有意に高く、紫外線は職業性曝露要因として位置づけられています。
安全配慮義務の観点からも、屋外作業者・外勤者・窓際勤務者に対しては紫外線対策を講じる必要があります。
◆ 効果的な紫外線対策(エビデンスレベルA〜B、米国疾病対策センター(CDC)、世界保健機関(WHO)など)
① 強い時間帯を避ける
- 午前10時〜午後2時の直射日光を避ける
- 屋外作業は可能であれば午前・夕方にシフト
② 日陰や屋内を活用
- 日陰でも紫外線量は日向の約50%
- 完全な遮断には屋内作業や屋根のある環境が必要
③ 物理的遮蔽
- 帽子:つば7cm以上で顔の紫外線曝露を30〜50%減
- サングラス:紫外線透過率1.0%以下のUVカットレンズ推奨(色の濃さではなくUVカット性能で選ぶ)
- 衣服:長袖・濃色・厚手素材で遮蔽率UP(UPF値参照)
④ 日傘の活用
- UVカット加工済みの日傘は紫外線曝露を最大90%カット
- 屋外移動の多い社員への貸与も有効
⑤ 日焼け止めの使用
- SPF:UVB防御指数(15〜30で日常用、30以上は屋外作業向け)
- PA:UVA防御指数(PA+++以上推奨)
- 使用のコツ:
- 出勤前に塗布
- 2〜3時間おきに塗り直し(汗や摩擦で効果低下)
- 顔・首・耳・手の甲も忘れずに
◆ 企業としてできる取り組み
- 就業管理
- 屋外作業の時間帯を調整する
- 夏場は休憩時間をこまめに設定する
- 物品支給
- 帽子、サングラス、日焼け止め、日傘などを配布する
- UVカット作業着を導入する
- 職場環境改善
- 作業場所への日除けを設置する
- 車両や作業車にUVカットフィルムを貼る
- 教育啓発
- 衛生委員会や社内研修で紫外線の健康影響と対策を周知する
◆ よくある誤解と注意点
| 誤解 | 実際 |
|---|---|
| 曇りの日は紫外線が少ない | 薄い雲ではUVBの80%以上が通過する |
| 色の濃い(暗い)サングラスなら安心 | 瞳孔が拡大するで、UVカット機能がないと逆に紫外線曝露増 |
| 日焼け止めは朝だけでOK | 2〜3時間で効果低下、塗り直し必須 |
| 屋内なら紫外線ゼロ | 窓ガラスを通過するUVAは届く |
◆ まとめ:紫外線対策は健康経営の一部
紫外線対策は、単なる美容や日焼け防止ではなく、労働衛生管理と健康経営の重要施策です。
屋外作業者や外勤者はもちろん、オフィス勤務者でも曝露リスクはゼロではありません。
企業が主体的に紫外線対策を講じることは、従業員の熱中症対策にもつながります。
今年から、ぜひ職場全体で紫外線対策の取り組みを始めましょう。
投稿者プロフィール

-
しながわ産業医オフィス 代表産業医
産業医としてこれまでに延べ3,000名以上の従業員の健康管理に携わる。
<保有資格>
泌尿器科学会認定専門医・指導医
テストステロン治療認定医
最新の投稿
 産業医コラム2026年1月31日職場における花粉症対策 ― 生産性低下を防ぐために ―
産業医コラム2026年1月31日職場における花粉症対策 ― 生産性低下を防ぐために ― お知らせ2025年12月27日年末のご挨拶
お知らせ2025年12月27日年末のご挨拶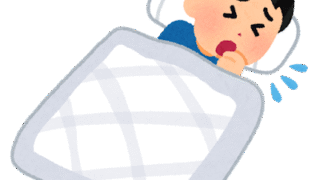 産業医コラム2025年11月30日冬の感染症対策2025:職場で防ぐインフル・ノロの集団感染
産業医コラム2025年11月30日冬の感染症対策2025:職場で防ぐインフル・ノロの集団感染 産業医コラム2025年10月23日ストレスチェック制度の運用ポイント――人事が押さえるべき視点を解説!
産業医コラム2025年10月23日ストレスチェック制度の運用ポイント――人事が押さえるべき視点を解説!