夏は要注意!?職場における食中毒対策
◆ はじめに:食中毒はどの職場でも起こりうる
食中毒と聞くと飲食店や食品工場を思い浮かべる方が多いですが、実際にはオフィスや工場の休憩室、社内イベントでも発生します。
厚生労働省の統計(令和6年)でも、事業所内での発生例は少なくありません。
一度発生すれば複数人同時発症、業務停止といった大きな損失につながります。
◆ 食中毒とは?(定義と発生状況)
定義:細菌・ウイルス・寄生虫・化学物質・自然毒などで汚染された食品を摂取することで起こる健康被害。
主な症状:腹痛・下痢・嘔吐・発熱・頭痛など。重症化すると入院や死亡例もあります。
特徴的なのは、食中毒の原因となる微生物は食品の色・味・においを変えないこと。見た目や匂いで判断できないため、予防が最重要です。
◆ 発生の季節性
- 細菌性食中毒:5〜9月(高温多湿で細菌が増殖しやすい)
- ウイルス性食中毒:冬季(特にノロウイルス)
◆ 予防の三原則(エビデンスレベルA)
- つけない:食品に病原体を持ち込まない
- 手洗いの徹底(WHO推奨の20秒以上、流水と石けん)
- 調理器具の洗浄・消毒、まな板や包丁の用途別使用
- ふやさない:病原体を増殖させない
- 食品は10℃以下で保存(冷蔵)、作り置きは避ける
- 室温放置は2時間以内
- やっつける:病原体を死滅させる
- 加熱は中心温度75℃で1分以上(ノロは85〜90℃で90秒以上)
- 冷凍や加熱による寄生虫対策(例:アニサキスは-20℃24時間以上)
◆ 主な原因と対策
1. ウイルス(例:ノロウイルス)【A】
- 原因:二枚貝(カキ等)、感染者の手指や便・嘔吐物からの二次感染
- 潜伏期:24〜48時間
- 対策:
- 調理者は体調不良時に作業しない
- 食品・調理器具の十分な加熱(85〜90℃で90秒)
- 嘔吐物処理は使い捨て手袋・マスク着用、次亜塩素酸ナトリウムで消毒
2. 細菌(カンピロバクター、サルモネラ、黄色ブドウ球菌等)【A】
- カンピロバクター:加熱不十分な鶏肉、非加熱の井戸水
- 対策:中心温度75℃1分以上の加熱、生肉と他食材の分離
- サルモネラ:卵、食肉、調理後の長時間常温放置
- 対策:冷蔵保存、手指消毒、十分加熱
- 黄色ブドウ球菌:手指の傷口から食品へ
- 対策:手袋着用、傷口保護、調理後は速やかに冷蔵
3. 寄生虫(アニサキス)【B】
- 原因:生魚(サバ、アジ、イカ等)
- 対策:-20℃で24時間以上冷凍、または60℃で1分以上加熱
◆ 職場での具体的な対策例
- 休憩室・給湯室管理
- 冷蔵庫の温度管理(10℃以下)
- 調理器具・スポンジの定期交換
- 消費期限切れ食品の廃棄ルール
- 弁当・ケータリング管理
- 配達から喫食まで2時間以内
- 夏季は保冷剤を使用
- 社内イベント(BBQ・忘年会等)
- 加熱用食材と生食用食材を分けて保管・調理
- 調理者の健康チェック
- 教育と啓発
- 衛生委員会での講話、ポスター掲示
- 新入社員研修に食品衛生教育を組み込む
◆ 食中毒発生時の対応フロー(エビデンスB)
- 患者の医療機関受診と診断確定
- 事業所への報告(人事・衛生管理者)
- 原因食品・状況の特定(保健所報告)
- 汚染区域・器具の消毒(次亜塩素酸ナトリウム)
- 関係者の就業制限(感染症法第18条)
- 腸管出血性大腸菌(O157等):陰性確認まで
- ノロウイルス:症状消失後かつ一定期間経過後
◆ エビデンスレベルと根拠
- Aレベル:WHO、厚生労働省ガイドライン、CDC等でRCTや系統的レビューのある対策(例:手洗い20秒以上、中心温度75℃加熱、冷蔵10℃以下)
- Bレベル:大規模観察研究や複数事例報告で有効性が確認されている対策(例:社内ルール整備、器具の定期交換)
◆ まとめ:食中毒対策は「習慣化」が鍵
職場の食中毒は「自分の職場には関係ない」と思った瞬間に起こります。
特に夏場や冬季のピーク時は、手洗い・温度管理・加熱という基本の徹底が最も有効です。
企業担当者の方は、衛生委員会での啓発・ルールの明文化・物品管理を通じて、食中毒ゼロ職場を目指しましょう。
投稿者プロフィール

-
しながわ産業医オフィス 代表産業医
産業医としてこれまでに延べ3,000名以上の従業員の健康管理に携わる。
<保有資格>
泌尿器科学会認定専門医・指導医
テストステロン治療認定医
最新の投稿
 産業医コラム2026年1月31日職場における花粉症対策 ― 生産性低下を防ぐために ―
産業医コラム2026年1月31日職場における花粉症対策 ― 生産性低下を防ぐために ― お知らせ2025年12月27日年末のご挨拶
お知らせ2025年12月27日年末のご挨拶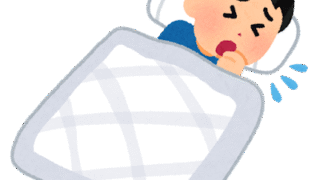 産業医コラム2025年11月30日冬の感染症対策2025:職場で防ぐインフル・ノロの集団感染
産業医コラム2025年11月30日冬の感染症対策2025:職場で防ぐインフル・ノロの集団感染 産業医コラム2025年10月23日ストレスチェック制度の運用ポイント――人事が押さえるべき視点を解説!
産業医コラム2025年10月23日ストレスチェック制度の運用ポイント――人事が押さえるべき視点を解説!


