36協定=安心ではない?人事が知っておくべき“長時間労働管理”の落とし穴
長時間労働への対応は、いまや企業としての信頼性や従業員の健康に大きく関わる重要なテーマです。
その中で人事担当者の方がよく誤解しているのが、「36協定を締結しているから、長時間労働にも対応できている」という考えです。
実は、36協定と“長時間労働者に対する健康管理”は別の制度であり、それぞれに求められる対応内容は異なります。本コラムでは、36協定との違いを整理したうえで、企業が実務上押さえるべき「長時間労働管理の要点」を解説します。
■ 36協定とは何か?
36協定(時間外・休日労働に関する協定届)とは、労働基準法36条に基づき、企業が労働者と合意して所轄労基署に提出することで、法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働を行わせることを可能にする制度です。
しかしこれはあくまで「残業させても良いという労使間のルール」であって、従業員の健康管理までを担保するものではありません。
■ 長時間労働者に対する健康管理とは?
厚生労働省の通達により、以下の基準で「長時間労働者」とされる従業員には、産業医による面接指導や就業上の措置が求められています。
- 月80時間超の時間外・休日労働がある従業員(直近1か月)
- 疲労の蓄積や体調不良が認められる場合(労働時間にかかわらず)
また、過労死等の労災認定基準においては、月100時間超または2〜6か月平均80時間超が重要なラインとされています。
つまり、36協定で「月45時間まで残業可」と定めていても、繁忙期の影響などで実際に従業員が月80時間以上の残業をしていれば、産業医の面接指導が必要になる可能性があるということです。
■ 企業が押さえるべき「長時間労働管理の要点」
では、36協定とは別に、企業はどのような実務対応をすべきなのでしょうか。以下の3点が要となります。
① 労働時間の客観的把握
ICカード、PCログ、勤怠システム等により、正確に労働時間を記録・把握することが求められます。当然、自己申告だけでは不十分です。
② 長時間労働者の早期把握と対応
月80時間を超えた時点で、該当者を把握し、以下の対応を検討します。
- 本人へのヒアリング(疲労感・不調の有無)
- 必要に応じた産業医面談の実施
- 面談結果に基づく就業措置(時間短縮、業務変更など)
③ 衛生委員会などでの対策検討
長時間労働の発生が常態化している場合、衛生委員会での対策検討が必要です。原因分析と業務改善の推進が、労働環境の改善につながります。
■ なぜ36協定だけでは不十分なのか?
36協定は「法律上の義務をクリアするための枠組み」にすぎません。
従業員の健康に配慮した職場づくりの観点では、“実態”に即した対応(健康管理、予防)が不可欠です。
また、過労死やメンタル不調による労災が発生した場合、36協定の有無ではなく、企業として健康管理にどれだけ取り組んでいたかが問われます。
■ まとめ
「36協定=長時間労働管理」ではありません。
人事担当者が押さえておくべきポイントは、法的な整備(36協定)+ 実態把握と健康管理の体制構築です。
長時間労働は、労働者の健康だけでなく、企業の生産性やレピュテーションにも直結する課題です。制度に頼るだけでなく、現場の声やデータに基づいた健康管理こそが、“真の働き方改革”の第一歩といえるでしょう。
投稿者プロフィール

-
しながわ産業医オフィス 代表産業医
産業医としてこれまでに延べ3,000名以上の従業員の健康管理に携わる。
<保有資格>
泌尿器科学会認定専門医・指導医
テストステロン治療認定医
最新の投稿
 産業医コラム2026年1月31日職場における花粉症対策 ― 生産性低下を防ぐために ―
産業医コラム2026年1月31日職場における花粉症対策 ― 生産性低下を防ぐために ― お知らせ2025年12月27日年末のご挨拶
お知らせ2025年12月27日年末のご挨拶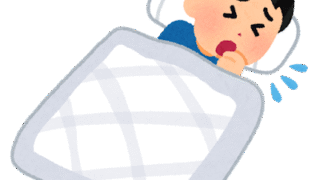 産業医コラム2025年11月30日冬の感染症対策2025:職場で防ぐインフル・ノロの集団感染
産業医コラム2025年11月30日冬の感染症対策2025:職場で防ぐインフル・ノロの集団感染 産業医コラム2025年10月23日ストレスチェック制度の運用ポイント――人事が押さえるべき視点を解説!
産業医コラム2025年10月23日ストレスチェック制度の運用ポイント――人事が押さえるべき視点を解説!


