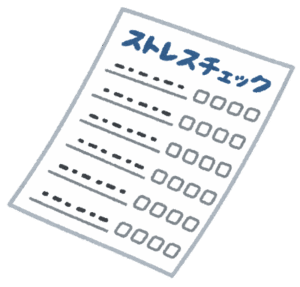職場におけるメンタル不調の基礎知識と対策
はじめに:増加し続けるメンタル不調
近年、働く世代のメンタル不調は増加の一途をたどっています。
うつ病の患者数は過去20年で約2〜3倍に増加し、精神障害に関する労災認定件数も右肩上がりです。さらに、自殺者の約4人に1人は会社員であり、その多くが直前にメンタル不調の診断を受けていたと報告されています。
もはやメンタルヘルスは一部の人だけの問題ではなく、すべての企業にとって避けられない課題となっています。
メンタル不調とは何か
「メンタル不調」とは必ずしも病名のつく精神疾患を指すわけではありません。心身にストレスがかかり、心理的・身体的な不調が表れている状態を広く含みます。
代表的なものには以下のような例があります。
- 精神疾患:うつ病、躁うつ病、適応障害など
- 身体症状:ストレス性胃潰瘍、過敏性腸症候群、頭痛、高血圧
- 行動変化:アルコール依存、買い物依存、対人トラブル
ポイントは「ストレス耐性には個人差がある」ということです。同じ状況でもある人は耐えられ、ある人は大きな不調に陥る。人事担当者が画一的に判断せず、一人ひとりに応じた支援が求められます。
職場でよくみられるメンタル不調のタイプ
実際の職場では、以下のようなタイプの不調が見られます。
- 古典的うつ病
真面目で責任感の強い社員が長時間労働で疲弊し、徐々にミスや欠勤が増え、ついには出社できなくなるケースです。治療と休養で回復は可能ですが、再発しやすいため復職後の業務調整が重要です。 - 非定型うつ病
職場環境でのみ症状が出やすいタイプで、「怠け」と誤解されやすいですが、環境調整や対話的な支援が必要です。 - 発達障害スペクトラム関連
能力は高い一方で、コミュニケーションの誤解やトラブルを起こしやすいケースです。上司からの指示を「具体的に、曖昧さなく」伝えることで働きやすさが改善する場合があります。
企業に求められる「4つのケア」と「3つの予防」
厚生労働省は、職場のメンタルヘルス推進の枠組みとして「4つのケア」を提唱しています。
- セルフケア:従業員本人が自分のストレスに気づき、対処する力をつける
- ラインケア:管理監督者が部下を支援し、業務量を調整する
- 事業場内ケア:産業医や保健師など社内の専門職による支援
- 事業場外ケア:医療機関や外部カウンセラーなど社外資源の活用
さらに、一次〜三次予防の考え方を応用して、
- 教育や情報提供での早期予防(一次予防)
- 不調者を早めに発見する(二次予防)
- 休職者を円滑に復職支援する(三次予防)
を組み合わせることが効果的とされています。
セルフケアの基本
セルフケアはすべての従業員が実践できる取り組みです。
基本は「生活リズムを整える」ことにあります。
- 睡眠を十分にとる(理想は7時間前後)
- 適度な運動や趣味で気分転換をする
- ストレスを一人で抱え込まず、早めに相談する
- アルコールや喫煙でのストレス解消に頼らない
研究によれば、月80〜100時間以上の残業を続けると健康障害のリスクが2〜3倍に増加することがわかっています。セルフケアと同時に、労働時間管理も不可欠です。
ラインケアの重要性
管理職が果たす「ラインケア」も極めて重要です。
部下の業務負荷を調整し、長時間労働を未然に防ぐことが一次予防となります。さらに、部下の話を傾聴し、努力や成果を認めることで、やりがいと自己効力感が高まります。
相談を受けた際に「頑張れ」と励ますだけでは逆効果になることもあります。大切なのは、事実に基づき冷静に観察し、共感的に耳を傾けることです。
早期発見と対応のポイント
メンタル不調は、日常の小さなサインとして現れることが多いです。
例えば、遅刻や欠勤が増える、能率が低下する、表情が暗い、ケアレスミスが増える、飲酒量が増えるなどです。こうした兆候が一週間以上続いた場合は要注意です。
対応の第一歩は「声かけ」です。その際は批判や説教ではなく、傾聴・受容・共感の姿勢を大切にしてください。
法的リスクと人事の責務
労働契約法第5条では、使用者に労働者の安全配慮義務が明記されています。
管理職には「危険を予知する義務」と「結果を回避する義務」があり、過重労働や強いストレス要因を放置すれば、労災認定や企業責任に発展するリスクがあります。
人事部門は、制度設計と職場環境改善をリードする立場として、この義務を果たす中心的な役割を担っています。
まとめ:企業全体で支えるメンタルヘルス
メンタル不調は誰にでも起こりうる問題であり、個人の努力だけに任せては解決できません。
セルフケア教育、ラインケアの実践、産業医や保健師による専門的サポート、そして必要に応じて外部医療機関へつなぐ仕組みを組み合わせることで、ようやく「企業全体で支える体制」が整います。
人事担当者は、その体制づくりを推進する重要な役割を担っています。日常の観察と早期対応によって、不調の芽を摘むことができます。
メンタルヘルス対策は法令遵守だけでなく、従業員の幸福度向上と企業の持続的成長に直結する「投資」でもあります。
これを機に、自社の取り組みをぜひ見直してみてください。
投稿者プロフィール

-
しながわ産業医オフィス 代表産業医
産業医としてこれまでに延べ3,000名以上の従業員の健康管理に携わる。
<保有資格>
泌尿器科学会認定専門医・指導医
テストステロン治療認定医
最新の投稿
 産業医コラム2026年1月31日職場における花粉症対策 ― 生産性低下を防ぐために ―
産業医コラム2026年1月31日職場における花粉症対策 ― 生産性低下を防ぐために ― お知らせ2025年12月27日年末のご挨拶
お知らせ2025年12月27日年末のご挨拶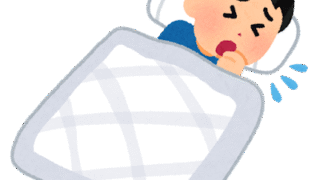 産業医コラム2025年11月30日冬の感染症対策2025:職場で防ぐインフル・ノロの集団感染
産業医コラム2025年11月30日冬の感染症対策2025:職場で防ぐインフル・ノロの集団感染 産業医コラム2025年10月23日ストレスチェック制度の運用ポイント――人事が押さえるべき視点を解説!
産業医コラム2025年10月23日ストレスチェック制度の運用ポイント――人事が押さえるべき視点を解説!